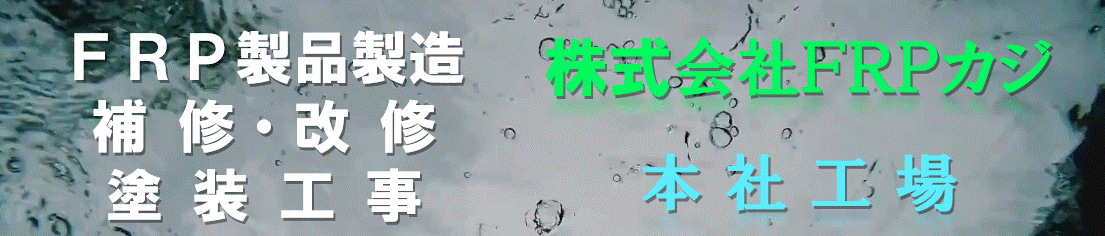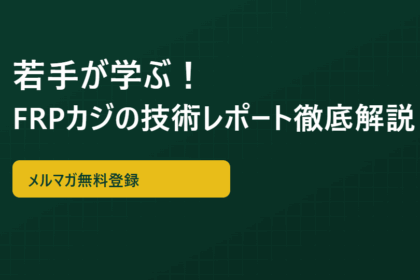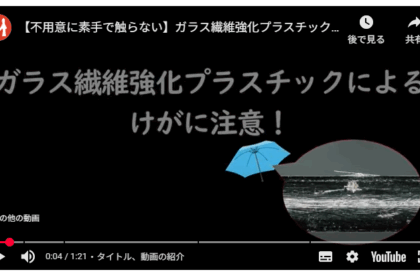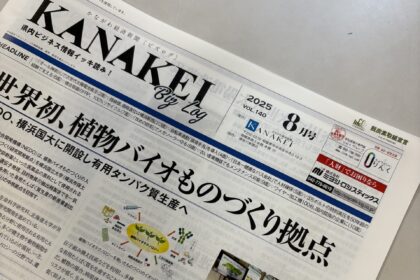株式会社 FRPカジR&Dセンター メールマガジン
◇◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇
◇◇ 技術評価受託の活用法と解説 ◇◇
◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◇◇
2024年5月16日
第八回:超音波厚さ計+Autodesk Fusion 360-クリップを作る
<目次> ─────────────
・R&D所有設備紹介+動画
・モデリング技術+動画
<R&D所有設備紹介+動画> ─────────────
・今回の紹介する設備仕様
超音波厚さ計 UDM-1100(日本電磁側器)
〈超音波厚さ計とは何か〉
超音波厚さ計とは、その名の通り厚みを計測するための装置の一種です。
この装置では、探触子(測定物に接触させる部分)の中の振動子で超音波を発生させ、
測定対象物の表面凹凸を埋めるために塗布した接触媒質(グリセリン等)を経由して超音波を入射させます。
入射した超音波は測定対象物の入射面の逆側にある反対面で反射し、
探触子へと戻ります。
これら一連の工程において、入射面と反射面での超音波の反射であるエコーを検知することで、
超音波が入射してから反対面で反射して帰ってくるまでの時間(伝播時間)を算出します。
この伝播時間と測定対象物を超音波が通過する際の音速から、
厚さを算出できるという仕組みです。
なお、音速は測定対象物を構成する材料の密度と弾性率に依存するため、固有の値を示します。
よって測定対象物の実測厚みから実際の音速を算出し、
その音速を測定条件に採用する校正の実施が厚み計測精度を高めるポイントとなります。
弊社所有の超音波厚さ計 UDM-1100(日本電磁側器)は、FRPやタイヤ、そして合成樹脂向けのポケットタイプの装置となります。
FRPやタイヤのような強化繊維(ガラス繊維等)とマトリックス樹脂やゴムからなる複合材料の場合、
強化繊維、気泡等による超音波の反射がノイズエコーとなってしまい、
上記の入射面と反対面のエコーをうまくとらえられない恐れがあります。
超音波厚さ計 UDM-1100は複合材料で頻発するノイズエコーが存在することを想定し、
ゲイン等の条件設定を複合材料向けに設定してありますが、
気泡や層間剝離等が多い、または大きい場合はそれ自身がキズエコーとなり、
正確な厚み計測は困難になります。
そのため、非破壊検査による内部欠陥有無の確認と組み合わせることも、
必要に応じて行うことが重要と考えます。
UDM-1100の仕様は以下の通りです。
・測定範囲:1.0~50.0mm(精度±0.1mm)
・誤差範囲:±0.1~±0.25mm
・音速調整範囲:500~9999m/sec
・使用温度範囲:-10℃~50℃
・質量:本体290g、探触子60g
〈実際の使用例・活用法〉
使用前に必ず校正を行いますが、校正にはこれから測定したい測定物の音速を設定する必要があります。
音速が未知の場合、校正は次のように行います。
① 本体、探触子、ケーブルをそれぞれ接続させます。
② 「VEL/POW」キーを押して電源を入れ、10秒ほど待ちます。
③ 再度「VEL/POW」キーを押し、音速の画面を表示させます。
④ 測定物の厚みをノギスやマイクロメーター等で計ります。
⑤ 測定物の材質からおおよその音速を設定します。
⑥ 測定したい箇所に接触媒質(グリセリン等)塗って、探触子を軽く押し当てます。
⑦ ④で計った厚さと一致するように↑または↓キーで厚みを変更します。
⑧ 変更後、測定を中断し、「VEL/POW」キーを押すと音速の確認ができます。
⑨ 再度「VEL/POW」キーを長押しし、画面にLOCKと表示されるのを確認します。
弊社では劣化診断の際に超音波厚さ計を活用しています。
一般的な劣化診断では、触診とバーコル硬度計による硬度検査を行います。
それに加え、弊社では検査対象物の設計図面と実測厚みを比較し、減肉等の劣化事象発生有無という別の観点からの診断を行います。
さらに社内で開発した技術を応用し、厚み測定に用いられている超音波による劣化診断を試みています。
この技術は現在社内で開発中であり、
一日も早い現場での活用に向け準備を進めています。
劣化診断の方法はHPにて公開しています。
・FRP製貯蔵タンクの劣化診断
https://x.gd/j3CnJ
・ R&D所有設備動画のURL
<モデリング技術+動画> ─────────────
〈モデリング作業のコツ〉
Autodesk Fusion 360-クリップを作る
1.「作成▼」から「線分」のコマンドを選択し、XYの中心座標をクリックします。
2. X軸方向に直線を描きます。適当な長さの位置でシフトを押しながらクリックします。
3. 描いた線と平行な直線を下部に描きます。2.でシフトを押すことによって、描いた線と
次に描いた線が円弧で自動的に結ばれます。
4. 2.を繰り返し、四本の平行した線を描くと円弧で結ばれたクリップの絵が出来上がります。
5. 寸法定義を行います。
6. 4.で出来上がった線がスイーブのパスとなります。最初に描いた直線の断面となる
中心点の位置に「サーフェス」コマンドから円を描きます。
7. 「スイーブ」コマンドを選択し、クリップをパス、プロファイルに円を指定してOKをクリックします。
・本モデリング技術の応用例
上記工程4.で出来上がったスイーブ用のパス(線)の断面にスケッチする形は、四角や三角、星型等、
どの様な複雑形状であったとしても、線同士がくっついて(わずかでも隙間がない状態)いる形であれば、
「スイーブ」でパスに沿った状態で押し出すことが可能です。
また、Fusion 360はバネ形状においてはパスを作らずとも、「作成▼」から「コイル」コマンドを使用し、簡単にバネのモデルを作成することが可能です。
・上記の概要に該当する動画のURL